化学プラントにかかるセーフテイ・アセスメントに関する指針の運用について |
改正履歴
標記については、昭和51年12月24日付け基発第905号をもって通達されたところであるが、その運用に
当たっては、下記の事項に留意のうえ遺憾のないようにされたい。
記
1 「3・2定性的評価(第2段階)」に示した診断項目は一例を示すものであり、事業場でここに定め
る診断項目と同程度の内容を盛り込むものが別にある場合には、それによって差し支えないものである
こと。ただし、その場合には、当該診断項目を計画の届出の際に添付させるよう指導すること。
2 「3・2定性的評価(第2段階)」については、別添<略>の『定性的評価関係法令(要約)』を参
照とすること。
3 「3・2・1の(a)立地条件の3)」この項においては、非常用電源(自家発電設備又は他系統から
の受電)が停電等の非常事態に対応できる程度に準備されているか、また、水槽、貯水池等についても
緊急冷却、消火等に際し、対応しうる能力があり、災害時に被害が拡大しない程度のものを備えている
かを検討するものであること。
4 「3・2・1の(a)立地条件の6)」この項においては、近接工場の間で排水溝や配管が連絡してい
て、爆発、火災等がこれらを通して伝ぱするおそれがある場合に、緊急閉鎖できるか、また、境界付近
に空地を置いているか、防火壁等の施設を設けているか等について検討するものであること。
5 「3・2・1の(b)工場内の配置の1)」この項においては、門やさくによって関係者以外の者や車
両等が出入りしないようにするもので、とくに危険度の高いプラントにおいては厳重に行う必要がある
ので検討するものであること。
6 「3・2・1の(b)工場内の配置の4)」この項においては、計器室は常に作業員が出入りし、集合
する場所であり、プラントの頭脳ともいうべきところであるから、災害の発生に際して被害を直接受け
るような位置に設けていないか、また、想定される爆風、火災、有害ガス、高熱物等が直接室内へ侵入
できない構造であるか等について検討するものであること。
7 「3・2・1の(b)工場内の配置の6)」この項においていう荷積み、荷卸し地区は、大量の危険物
の集積が考えられるため、危険度の高いプラントに近接していると、一方の災害発生によって相互に大
被害を与え合うこととなるので、できるだけ離れた場所に設けるべきであり、このことを考慮して検討
するものであること。
8 「3・2・1の(b)工場内の配置の7)」この項の「埋設により」は地下タンクを意味し、地上に出
ているものを土等で覆ったものは含まれないものであること。
9 「3・2・1の(b)工場内の配置の8)」この項においていう廃棄物処理設備は、有害ガスの漏えい、
悪臭の発生、危険物の爆発、火災等のおそれがあるため、これを工場の敷地内に設ける場合には、操業
プラントとは隔離して設けるべきであること。また、一般民家等と近接して設けることは公害となるお
それがあるので、居住区とは離し、被害を与えるおそれのない地域を選定しなければならないものであ
ること。
風向きも同様に考慮すべきものであること。
10 「3・2・1の(b)工場内の配置の9)」この項においては、救急車、消防車等が少なくともすれ違
える程度の通路が必要であることにかんがみ、このことを考慮して検討するものであること。
11 「3・2・1の(c)建造物の2)」この項においては、プラントの建設地盤が軟弱な埋立て地等の場
合には、地質を調査することにより安全性を判断すべきで、その場合地質図等を作成して検討するもの
であること。
12 「3・2・1の(c)の建造物の9)」この項においては、プラントで使用する水その他の液体を排水
するための設備の能力をチェックするもので、注水する能力と排水する能力とのバランス等を検討する
ものであること。
13 「3・2・2の(c)輸送、貯蔵等の4)」この項においていう「不安定物質」とは、過酸化物、ジア
ゾ化合物等のように、比較的小さいエネルギーで分解を起こし、発熱、発火、爆発等を生ずるような物
質をいうものであること。
14 「3・2・2の(c)輸送、貯蔵等の7)」この項においては、配管内における液体、とくに引火性の
液体については、その流速をなるべく小さくすることにより発生する静電気量を最小限にしなければな
らないものであること。なかでも非導電性の液体は流速が大きいほど静電気の蓄積が大きくなり、発火
の原因となりやすいことを考慮すべきものであること。
15 「3・2・2の(d)プロセス機器の5)」この項においては、プロセス機器について、反応器、ポン
プ等の温度、圧力等に異常事態が発生した場合に、自動的に通常の状態に復帰できるようなシステム、
さらに異常事態が進行した場合には、ブローダウン回路への切換えができるようなシステムの設計が織
り込まれているか否かを検討するものであること。
16 「3・2・2の(d)プロセス機器の10)」この項においては、安全弁、警報装置、消火設備、緊急し
ゃ断弁等が異常時に作動した場合、その機能が十分発揮できるように、直接火災や爆風にさらされぬよ
うに保護されているか等について検討するものであること。
17 「3・3の定量的評価表」この項における反応エレメントに係る取り扱う物質温度、圧力等について
は別紙3(その1)(その2)「定量的評価に関する参考資料」を参考にすること。
18 「3・3の定量的評価表の3温度」この項においていう「物質の発火温度」については、測定する装
置や方法によって数値が異なるので、当面、日本化学会編防災指針第1集”諸物質の火災危険性”のな
かに示されている発火点を適用すること。
ただし、前記の防災指針に記載されていない物質の発火温度については、別紙1のいずれかの方法に
より測定したものを適用すること。
19 「3・3の定量的評価表の5操作」この項においていう「Qr/CpPv」については別紙2を参考とする
こと。
(別紙 1)
発火温度の測定法
1 気体の場合
(1) 導入法
一定温度に保った容器内に混合気を導入して、発火がおこるかどうか調べる方法で、発火がおこ
らなければ温度を上げてこれを繰り返す。混合気の代わりに燃料または酸化剤をあらかじめ入れて
おくこともある。器壁の影響が大きい。
(2) ポンプ法
容器中に混合気をつめ、これを加熱して発火のおこる温度を発火温度とする方法である。発火は
圧力の急激な変化で知る。気体の温度分布が一様でなく、器壁の影響が大きい。
(3) 流通法
加熱管中に混合気を流し、発火する温度を求める方法で、予熱の影響は少ないが、流速に依存す
るようになる。同心管法はこの方法の一つだが、同心管で別々に加熱した可燃ガスと空気(または
酸素)を送り、出口でまぜ合わせて発火有無を調べるもので、発火がおこらなければ、空気をさら
に加熱する、予熱の影響はさらに少なく、混合も十分であり、器壁の影響もさけられる。気体の発
火温度測定法としては、最も信頼性が高い。図1に装置の例を示す。
(4) 断熱圧縮法
円筒容器に混合気をつめ、ピストンを落下させ、圧縮により発火させる。発火がおこったときの
ピストンの位置、すなわち、圧縮後の体積から断熱圧縮を仮定して、次式から発火温度を求める。
T2/T1=(V1/V2)r−1=(P2/P1)1−(1/r)
ただし、T1:混合気の初期温度、T2:発火温度、V1P1:はじめの体積、圧力、V2P2:発火時
の体積、圧力、r:気体の定圧、定容比熱の比
図2に装置の例を示す。
(5) 衝撃波管法
衝撃波管を用いて衝撃波を発生し、それによって混合気を発火させる。温度は衝撃波の速度の測
定値から、エネルギー、質量、運動量の保存を考えて計算する。
(6) 予熱法
混合気をあらかじめ発火温度より低いある温度まで加熱しておき、次に発火するまで別のエネル
ギーを与える。予熱温度が発火温度に近いと、与えるエネルギーは少なくてすむので、それを利用
している。
2 液体または固体の場合
(1) 油滴法
粉末、油滴などを一定温度に保った金属、磁製またはガラス製などのるつぼに滴下して発火の有
無を調べるもので、るつぼ法ともいう。図3に示したのはASTM D2155−63Tで定められた装置で
少量(0.1cc程度)の試料を0.25〜1ccの注射器を用いて、あらかじめ所定の温度に加熱しておい
た電気炉中の200mlのエルレンマイヤーフラスコに注入し、5分間暗くした部屋で観測する。発火
フラスコ内で急に炎を生じることで確認できる。試料の予熱温度を増減する一連の測定を行い、発
火がおこる最低温度を発火温度とする。このほかよく用いられているものにMoore法があり、装置
を図4に示す。測定に当たっては、鋼塊を加熱しながら、酸素(空気)を毎秒3気ほうの割合でる
つぼ内に送入する。るつぼ内が所要温度になったとき、ビュレットから試料を1滴るつぼの中央に
滴下して発火の有無を調べる。この方法はASTM法と比べて、酸素(空気)を送り込む点に特長が
ある。
(2) 油浴法
試料を入れた容器を油浴に入れて温度を上げ、発火時の浴の温度を読む。
(3) 発熱法
試料を一定速度で加熱しながら試料内外の温度を測定し、両者の交わったところを発火温度とす
る。試料の大きさが影響し、大きいほど低くなる傾向がある。
(4) 重量法
石英スプリングや熱天びんなどを用いて、試料を加熱しながら重量を測定し、減少速度が大きく
なる点を発火温度とするものである。
(5) 接触法
一定温度に保った金属などに試料を接触させて発火温度を調べる。
3 発火温度の測定上の注意
(1) 発火おくれと発火温度の間には図5のような関係があるので、おくれ時間をどうとるかによって
発火温度そのものが異なってくる。おくれ時間を無限大にとったときの温度(最低発火温度)、0
にとったときの温度(真発火温度)などと区別することがある。一般に発火おくれ(γ秒)と発火
温度(T0K)の間には次の関係がある。
logγ=(0.22E/T)+B
ここで、E:みかけの活性化エネルギー〔cal/mol〕、B:定数である。したがって発火おくれ
の対数をI/Tに対してプロットすれば、図6に示すように直線となるので、そのこう配からみか
けの活性化エネルギーを求めることができる。
(2) 電気炉で混合気を加熱する場合と、気体で固体を加熱する場合、気体一固体間の熱伝達が相違す
るため、両者の温度は同じでない。
(3) 発火前の加熱が長いと、反応、分解などによって物質が変化するので注意しなければならない。
また、ゆるやかな酸化による発熱や発光と発火とは区別する。
(4) 部分加熱による発火温度は全面加熱法により高くなる。
(5) 気体の状態で測定した発火温度は、液体の状態での測定値より高い。
(6) 混合物の発火温度は、原則として成分の発火温度の中間にくる。(安全工学便覧より抜すい)
(別紙 2)
Qr/CpρVの説明
化学プラントにおける機器のうちで、反応器、加熱炉等のように、エレメント内で発熱反応が起こって
いるものは、それが正常に操作されている状態では、ほぼその発熱量に相当する冷却が行われているはず
である。ところが、たとえば除熱機能に異常が生じた場合には、その熱負荷すなわち内部での発熱速度が
大きいほど、異常による温度上昇速度は早く、潜在的危険性は大きい。
そこで、熱収支の式に基づいて以下に示す温度上昇速度を発熱による危険性の評価に用いることにする。
(熱の蓄積速度)=(熱の流入速度)−(熱の流出速度)−(除熱速度)+(反応等による発熱速度)(1)
集中系の連続反応器を例にとると、次式となる。
| CpρV |
dT |
=−CpρF(T−To)−UA(T−Tw)+Qr
(2) |
| dθ |
ここで、Cpρはそれぞれエレメント内の物質の比熱 、密度
、密度 Qrは反応による発熱速度
Qrは反応による発熱速度
 で反応熱と反応速度の積に相当する。Vはエレメントの容量〔m3〕、Fは供給流量
で反応熱と反応速度の積に相当する。Vはエレメントの容量〔m3〕、Fは供給流量 、T、
To、Twはそれぞれエレメント内、供給流体、冷却壁の温度〔℃〕、U、Aは、それぞれ伝熱係数
、T、
To、Twはそれぞれエレメント内、供給流体、冷却壁の温度〔℃〕、U、Aは、それぞれ伝熱係数
 、伝熱面積〔m2〕、θは時間hrである。
温度上昇速度は次式となる。
、伝熱面積〔m2〕、θは時間hrである。
温度上昇速度は次式となる。
| dT |
= |
Qr |
− |
F |
(T−To)− |
UA |
(T−Tw) |
dθ |
CpρV |
V |
CpρV |
(3)
すなわち、最も厳しい条件下である除熱機能の停止の場合の上昇速度は第1項のみとなり、
(4)
分布系の反応器あるいは回分式の反応器については、発熱の局所的な範囲あるいは時間帯の選び方によ
って上記の値が異なることになるが、その場合には危険性を過小評価しないという前提の下に代表的な条
件、たとえば反応初期の領域を選択するよう配慮する。
操作条件が通常の条件から25%変化することにより、この危険範囲に入る場合とは、反応の活性化エネ
ルギーが大きい場合あるいは副反応による発熱が顕著になる場合など、運転条件たとえば温度の上昇、空
間速度の低下、濃度の増加などによって発熱が大きく促進されるおそれのある状況を考慮したものである。
注)4式のCpρとしては、次のものを適用すること。
| (Cpρ)= |
(Cpρ)gVg+(Cpρ)lVl+(Cpρ)sVs |
V |
(V=Vg+Vl+Vs)
(Cpρ)g、(Cpρ)l、(Cpρ)sは、それぞれエレメント内の気体、液体、固体状のものの比熱と
密度の積
Vg、V、Vsは、それぞれエレメント内の気体、液体、固体状のものの体積
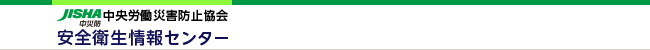
、密度
Qrは反応による発熱速度
で反応熱と反応速度の積に相当する。Vはエレメントの容量〔m3〕、Fは供給流量
、T、 To、Twはそれぞれエレメント内、供給流体、冷却壁の温度〔℃〕、U、Aは、それぞれ伝熱係数
、伝熱面積〔m2〕、θは時間hrである。 温度上昇速度は次式となる。